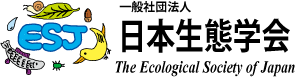会長からのメッセージ -その6-
「再生可能エネルギーの推進と生態系・生物多様性の保全に関する基本的な考え方」
2020年10月に菅義偉首相が「温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロにする」目標を掲げたことは、みなさんの記憶に新しいことと思います。地球環境問題を大きな研究課題のひとつとする日本生態学会は、この野心的な目標を大いに歓迎するものです。ただ一方で、日本各地ではメガソーラーや風力発電施設の環境影響が危惧されており、日本生態学会会員の間では、発電所建設が引き起こす生態系や生物多様性に対する影響が懸念されているところでもあります。
わたしは日本生態学会会長として、2020年12月に「再生可能エネルギータスクフォース」を会長の諮問組織として設置し、大学や研究機関の生態学の専門家だけではなく、環境法の専門家、事業者関連機関の研究者、合意形成を専門とする生態学会外の専門家の計11名のメンバーで議論をお願いしてきました。2021年3月17日に、その最初の成果物として答申案をいただきました。
2021年3月17〜21日に開催された日本生態学会第68回大会においてさまざまな議論を経て、本日3月22日付で日本生態学会会長名で、以下に「再生可能エネルギーの推進と生態系・生物多様性の保全に関する基本的な考え方」を意見表出することにいたしました。
この基本的考え方は、日本生態学会会員のみなさんが再生可能エネルギー発電所建設計画の引き起こす生態系や生物多様性に対する影響に関して助言を求められた場合に参考にしていただくとともに、再生可能エネルギー管轄諸官庁や発電所事業者関係のみなさんにはわたしたちがどのような懸念を持っているかをあらかじめ知っていただき、事業を円滑に進めていただくためのものです。
わたしたち日本生態学会は、再生可能エネルギーの推進に積極的に協力するとともに、生態系や生物多様性に対する配慮に関しては専門家として適切な助言を行っていくつもりです。今後もこの「再生可能エネルギータスクフォース」は勉強会と議論を重ねて、より実践的な手引き書などを作成していくことを予定しています。
2021年3月22日
日本生態学会会長 湯本 貴和
再生可能エネルギーの推進と生態系・生物多様性の保全に関する基本的な考え方
―日本生態学会自然再生エネルギータスクフォース答申―
※ PDF版![]() (以下と同じ内容です)
(以下と同じ内容です)
日本生態学会は、湯本貴和会長の諮問機関として、11人の専門家からなる自然再生エネルギータスクフォースを設置し、2020年11月から2021年3月まで計4回にわたる会議を開催し、再生可能エネルギーの推進と生態系・生物多様性の保全に関して検討を行ってきた。以下は2020年度における検討結果を簡潔にまとめたものである。
2015年に合意されたパリ協定の目標を達成するため、2050年にカーボンニュートラルを実現することは不可欠であり、2020年10月に菅首相が、2050年までに温室効果ガスの排出を全体的にゼロとし、脱炭素社会を実現することを宣言したことは気候変動緩和策の推進において有意義である。
近年、再生可能エネルギーの導入が進行しており、たとえば北海道だけでも陸上風力発電が300基、洋上風力発電を含めると400〜500基が建設・計画されている。今後、カーボンニュートラルの目標に向け、この動向はさらに加速するものと考えられる。そこで懸念されるのは、自然環境への影響である。すでに稼働している風力発電施設でも、猛禽類や渡り鳥の衝突、海浜植物群落や尾根上の植物群落への影響、取り付け道路や送電線の建設による影響などが問題となっている。陸上風力発電は、景観、騒音等、住環境への影響が大きいことや立地可能なスペースに限界があることから、今後、洋上風力発電が増えてくることが予想される。
また、大規模な太陽光発電施設(メガソーラー)は、二次林、植林地、草地などの里地里山の土地を改変して設置されることが多く、景観破壊や土砂崩れ等の災害を引き起こすばかりでなく、里地里山の生物多様性への影響が問題となっている。さらに、地熱発電の場合は、国立公園の特別地域等、自然保護上重要な地域に地熱エネルギーの賦存が集中していることから、保全上の価値が特に高い場所への影響が懸念されている。
気候変動と生物多様性は、1992年の環境と開発に関する国連会議(地球サミット)において議論され国際条約が締結された。気候変動問題はグローバルかつ将来世代の問題であるのに対して、生物多様性はローカルで現世代の問題であるという捉え方をされ、将来の環境問題解決のためには、ローカルな環境問題には目をつぶるべきだという議論も聞かれる。しかし、気候変動対策と生物多様性保全は、ともに将来世代の利益につながる重要な問題であり、一方の問題解決のため、もう一方を犠牲にすることは望ましくない。気候変動対策と生物多様性保全のいずれもが両立するような最適解を見つけることが望ましい。
そのためには、再生可能エネルギー施設を検討する段階において、生物多様性保全上重要な地域や猛禽類の生息地や渡り鳥の移動ルートなどをあらかじめ回避することにより、生態系や生物多様性に配慮した立地選定をすることが最も重要である。また、立地選定の適正化のためには野生生物に関する科学的知見だけではなく、すでに供用中の再生可能エネルギー施設におけるモニタリング調査データが極めて重要であり、その蓄積と公開が望まれる。
「海洋再生可能エネルギー発電施設の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(以下、再エネ海域利用法)」や、「地球温暖化対策の推進に関する法律改正案(以下、温対法改正案)(2021年3月2日閣議決定)」においては、再生可能エネルギー施設の促進区域を指定するゾーニングの考え方が示されている。また環境省も、環境アセスメントデータベース(EADAS)などを通じて鳥類のセンシティビティマップを公開するなど科学的根拠に基づいたゾーニングの基礎となるデータを提供している。これらの法律や制度に基づき、専門家や住民の合意のもとに、再生可能エネルギー施設の適正な立地選定がなされることが重要である。
日本生態学会には、生物多様性保全上重要な生態系、重要な鳥類の移動ルートなど、生態系や生物多様性に配慮した立地選定や自然環境へのインパクトが少ない計画立案に役立つ知見を有するメンバーが所属している。個々の再生可能エネルギー施設の計画や、地方公共団体が法律に基づいた実行計画の策定を行う際に、調査や助言が可能な専門家を紹介することも可能である。
本タスクフォースは、とくに風力発電、太陽光発電の適正な立地選定ならびに地方公共団体の実施計画に関して以下の3点を提言する。
1、風力発電の適切な導入のために必要なこと
2012年から風力発電事業が環境影響評価法の対象となり、現在119件が完了、302件がアセスメント実施中となっている。風力発電は1万kW以上の施設が環境影響評価法の第1種事業の対象に、7500kW以上〜1万kW未満が第2種事業の対象になっている。これに対して、風力発電促進のため、環境影響評価法の第1種事業となる規模要件を1万kWから5万kWに引き上げるべきだという意見が出ている。5万kWの風力発電施設は、海岸や尾根上に幅100m、全長5kmにわたる風車が立ち並ぶ面積に相当し、しかもこれには取り付け道路や送電線による改変面積は含まれない。
風力発電施設の計画にあたっては、生物多様性の保全上重要な地域、猛禽類の生息地や渡り鳥の移動ルートなどをあらかじめ回避し、生態系や生物多様性に配慮した立地選定を行うことが最も重要である。それがアセスメントの手戻りを防ぎ、結果として環境影響評価のプロセスの短縮化につながると考えられる。環境影響評価法の対象外となったとしても、生物多様性の保全上重要な地域に計画すれば、影響回避のための調査や生物多様性保全とのコンフリクト解消のために時間を要し、結局のところ時間短縮にはつながらない場合が多い。
また、環境影響評価に関しては、国の環境影響評価法と地方公共団体の環境影響評価条例が関連していることから、国が法律の規模要件を変えれば、地方公共団体の規模要件も変更せざるを得ない。またこれまで風力発電事業を環境影響評価条例の対象としていなかった自治体は、条例を改正する必要が出てくる。これらの改正を進めるには、相当な時間が必要となる。
風力発電施設の立地選定の適正化には、既設の風力発電施設の環境影響評価図書や、供用後の事後調査の公開が有効である。しかし残念ながら、発電所事業の環境影響評価図書は縦覧期間中のみ限定的に公開されており、事後調査報告書については環境大臣への報告義務がない、事後調査報告書が公開されていないなど、風力発電施設の適正な立地選定の障害となっている。
風力発電施設の適切な導入のためには、環境影響評価図書、事後調査報告書の公開を進め、それに基づいた全国的なゾーニングを推進することが重要である。
2、太陽光発電の適切な導入のために必要なこと
2020年から太陽光発電事業は環境影響評価法の対象となり、現在2件が完了、8件がアセスメント実施中である。太陽光発電は、4万kW以上の施設が環境影響評価法の第1種事業に、3万kW以上〜4万kW未満が第2種事業になっている。4万kWの太陽光発電施設は、1km四方にわたり太陽光パネルが設置される面積に相当する。国内には500kW以上の風力発電施設が8700箇所以上あるにもかかわらず、環境影響評価法に基づく環境アセスメントが行われているのは年数件に過ぎず、多くが地方公共団体の条例によって対処しているのが実情である。
地方自治研究機構によれば、再生可能エネルギーに関して条例を制定した自治体は、2012年に固定価格買取制度(FIT)が施行されてから急速に増加し、2014-2019年度までが78自治体、2020-2021年が51自治体となっている。これらの条例では、抑制区域等を設定し、その区域では太陽光発電施設の建設を禁止または規制し、それ以外の地域では届出制とするなどの事例が多い。しかし、自治体の条例という性格上、違反に対しては、氏名の公表までが限界であり、過料を課している場合でも1~5万円程度である。
一例として、静岡県富士宮市の「富士山景観と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」は、面積1000m2、高さ10m以上の施設を対象とし、条例に基づいて設定した抑制区域内では市長の同意がない限り設置は許可されず、抑制区域外でも景観への影響が出ないよう事業者と現地に行って指導している。違反事例が出ないよう、毎月パトロールを実施するなど、市役所職員の不断の努力によって条例の実効性が保たれている。
このように、太陽光発電施設の立地にあたっては、景観、住環境への影響に配慮するとともに、生態系・生物多様性への影響や土砂崩れなどの災害を回避する適正な立地選定のため、地方公共団体による実行計画の策定を推進することが重要である。
3、再生可能エネルギー施設の生態系や生物多様性に配慮した立地選定と実行計画の策定の推進
再生可能エネルギー施設による生態系・生物多様性への影響は、施設の規模だけではなくその立地によって影響の大小が大きく左右される。再生可能エネルギー施設による影響を回避するためには、生態系や生物多様性に配慮した立地選定が最も重要であり、計画の早い段階における自然環境への配慮が求められる。
洋上風力発電に関しては、再エネ海域利用法に基づき、現在11の海域において促進区域の選定が進められている。その多くが、東北地方日本海側や九州沿岸部に立地しているが、唯一太平洋側に位置する銚子沖は、伊豆諸島と北海道を結ぶオオミズナギドリの渡りのルートに位置するなど、生物多様性への影響に関して十分な配慮がなされているとは言い難い。
陸上風力発電ならびに太陽光発電に関しては、今後の温対法改正によって、地方公共団体による実行計画の策定が努力義務となるが、再生可能エネルギー施設建設による生態系・生物多様性への影響を防ぐためには、促進区域のみではなく、保全区域の設定が必要である。保全区域の設置にあたっては、自然公園等、法的な保護担保措置がとられている区域はもちろん、植物群落レッドデータブック、生態系レッドリスト、重要湿地等、国、地方公共団体、公益法人等によって選定された区域についても考慮に入れるべきである。温対法改正では、促進地域に計画される再生可能エネルギー施設については、環境影響評価法の配慮書手続きを省略することとなるため、実行計画の策定にあたっては、地域住民に加えて、地域の自然環境に詳しい専門家が参加して促進区域、保全区域の検討を行う体制づくりが求められる。